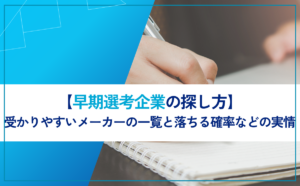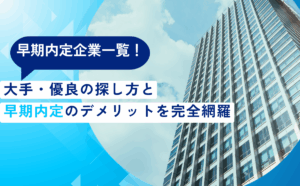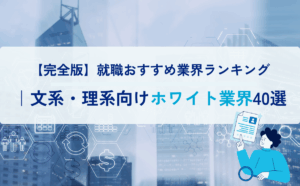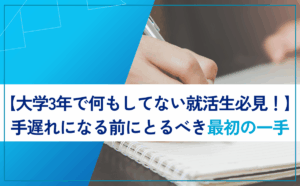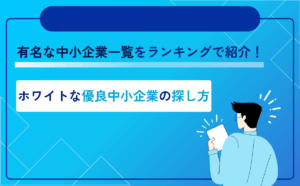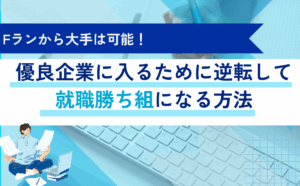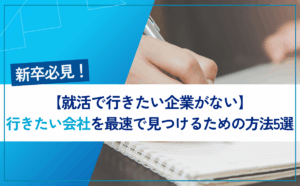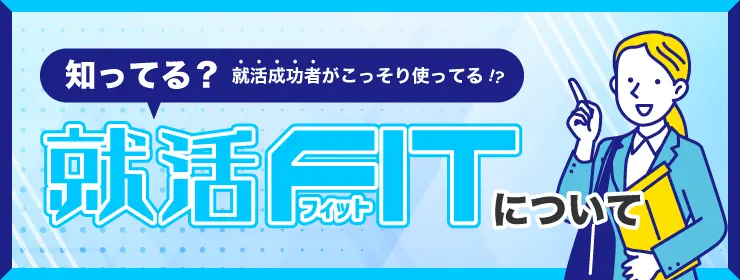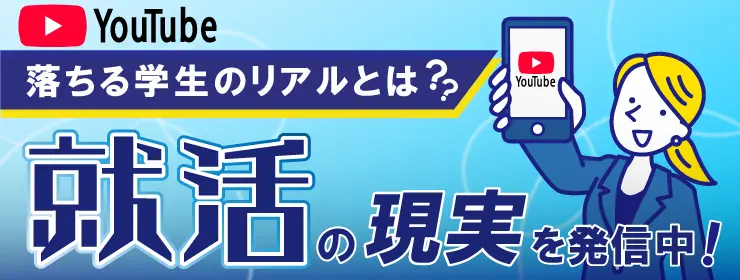今すぐ登録して
\勝つための就活を始めよう!/
就職活動の業界の決め方|業界選び診断でわかる志望業界の絞り方
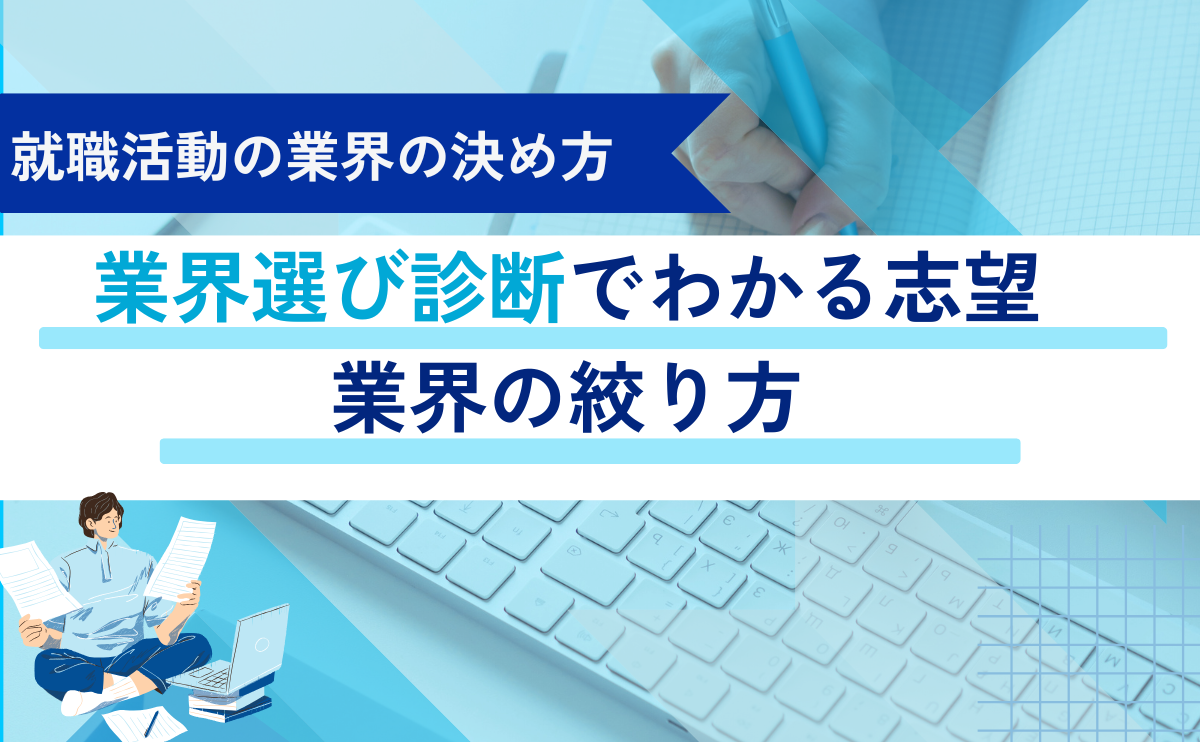
就職活動を進める中で、「どの業界に進めばいいかわからない」という悩みは多くの学生が抱えるものです。
しかし、正しい手順で自己分析と業界研究を進めれば、自分だけの「軸」を見つけ、納得のいく業界の決め方ができます。
この記事では、行きたい業界が見つからない原因から、具体的な業界の決め方・絞り方を5ステップで解説し、役立つ適職診断ツールも紹介します。
- 自分のやりたいことが分からず、志望業界を絞り込めない就活生
- 世の中にどのような業界があるのか、全体像を把握できていない就活生
- 自分に合った業界の具体的な見つけ方や決め方を知りたい就活生
就活で「行きたい業界がない」となる4つの原因
就職活動で志望業界が見つからない背景には、いくつかの共通した原因が存在します。
これらを理解することが、納得のいく業界の決め方への第一歩となります。
自分の強みや興味を理解できていない
自分が何にやりがいを感じるのかが曖昧なままでは、数ある業界の中から特定の分野に魅力を感じることは困難です。
就職活動における業界の決め方の基礎は、自分自身を正しく知ることから始まります。
どんな業界があるのか知らない
多くの学生は、消費者向けのBtoC企業など、一部の業界しか認識していません。
視野が狭いままでは、自分に最適な就職先や業界と出会う機会を失ってしまいます。
まずは世の中にどのような業界があるのか、全体像を把握することが重要です。
「大手」などのイメージだけで判断している
業界の将来性や働き方の実態は、企業の規模だけでは測れません。
イメージだけで判断せず、各業界の実態を多角的に調べることが、ミスマッチのない就職先の決め方につながります。
自分に合う業界はないと思い込んでいる
重要なのは、自分の中で譲れない軸を明確にし、優先順位をつけることです。
完璧な業界を探すのではなく、自分の価値観に最も近い業界を見つけるという視点を持ちましょう。
【5ステップ】就職する業界の決め方・絞り方
自分に合った業界を見つけるためには、体系立てられたステップに沿って進めることが不可欠です。
ここでは、自己分析から企業研究まで、具体的な業界の決め方を5ステップで解説します。
Step1. 自己分析で「自分の軸」を明確にする
Will(何がしたいか)、Can(何ができるか)、Value(何を大切にしたいか)の3つの視点から自分を掘り下げ、今後の業界選びの判断基準を明確にしましょう。
過去の経験を振り返り、自分の興味・関心、強み・スキル、そして働き方に関する価値観を整理することが重要です。
Step2. 業界研究で選択肢を広げる
就職情報サイトや業界地図などを活用して業界の全体像を把握し、少しでも興味を持った業界を複数リストアップしましょう。
この段階では厳密に絞り込まず、先入観を捨てて幅広く情報を集めることが大切です。
Step3. 業界の将来性や特徴を調べる
市場規模の成長性や安定性といった客観的なデータに加え、業界ごとの平均年収や働き方の文化などを調べましょう。
自分の価値観(Value)と照らし合わせながら、その業界が自分に合っているかを検討します。
Step4. 自分の軸と業界の特徴を照らし合わせる
Will・Can・Valueの観点から、それぞれの業界がどれだけ自分にマッチしているかを評価しましょう。
このマッチング作業を通じて、自分にとって魅力的な業界が3〜5つ程度に絞られてくるはずです。
Step5. 業界内の企業を調べて解像度を上げる
同じ業界でも企業によって事業内容や文化は大きく異なります。
企業説明会やインターンシップに参加し、働くイメージを鮮明にすることで、具体的な志望動機が形成されていきます。
これらの悩みは全て就活エージェント「キャリペン」に任せてください。自分自身で自己分析をしてしまうとどうしても偏りがでてきます。そこで、専任のプロのアドバイザーを頼ることで客観的な自己分析や業界研究ができます。また、完全無料でES添削や面接練習などの内定獲得までサポートします。
就活おすすめの業界診断ツール3選
自己分析や業界の決め方に悩んだ際は、客観的な視点を取り入れられる適職診断ツールを活用するのも有効です。
ここでは、おすすめのツールを3つ紹介します。
適性診断AnalyzeU+

自分では気づかなかった潜在的な強みを発見し、それを活かせる業界のヒントを得るために役立ちます。
診断結果をもとに企業からオファーが届く可能性もあります。
キャリアパーク「適職診断」

診断結果ではおすすめの業界や職種が具体的に提示されるため、「どの業界から調べればいいかわからない」という就活生にとって、業界研究の良いきっかけになります。
キミスカ「適性検査」
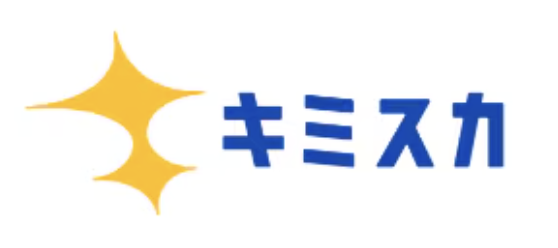
自分の性格や価値観に合った社風の業界や企業を見つけたいと考えている就活生におすすめで、診断結果を見た企業からスカウトが届くこともあります。
就活の業界選びでよくある質問
業界の決め方を進める上で、多くの就活生が抱く疑問について回答します。
業界はいつまでに決めるべきですか?
多くの企業が3月から採用活動を開始するため、それまでに方向性を定めておくことで、企業研究などに十分な時間をかけ、準備を有利に進めることができます。
複数の業界を受けるのは不利になりますか?
ただし、その際は業界を横断する自分なりの「就活の軸」を明確に説明できることが重要です。
一貫した軸があれば、複数の業界を受けていても志望度の高さを伝えることができます。
就活で8大業界とは何ですか?
- メーカー:自動車や食品など、モノを作る業界
- 商社:国内外で様々な商品を取り引きする業界
- 小売:百貨店やスーパーなど、消費者に商品を販売する業界
- 金融:銀行や証券、保険など、お金に関わるサービスを提供する業界
- サービス:人材や旅行、コンサルティングなど、形のないサービスを提供する業界
- ソフトウェア・通信:ITサービスや通信インフラなどを提供する業界
- マスコミ:テレビや新聞、広告など、情報を発信する業界
- 官公庁・公社・団体:国や地方自治体、公的な団体
これらの分類を参考に、幅広い業界に目を向けてみましょう。
まとめ
本記事では、就職活動における業界の決め方について、行きたい業界がない原因から具体的な5つのステップ、おすすめのツールまでを解説しました。
最も重要なのは、自己分析を通して自分だけの「軸」を明確にすることです。
その軸を基準に、広い視野で業界研究を進め、自分に合った選択をしてください。
この記事で紹介した方法を実践し、納得のいく就職活動を実現しましょう。これらの悩みは全て就活エージェント「キャリペン」に任せてください。自分自身で自己分析をしてしまうとどうしても偏りがでてきます。そこで、専任のプロのアドバイザーを頼ることで客観的な自己分析や業界研究ができます。また、完全無料でES添削や面接練習などの内定獲得までサポートします。