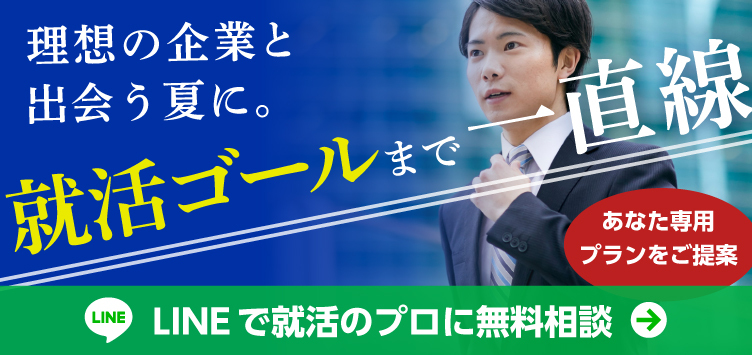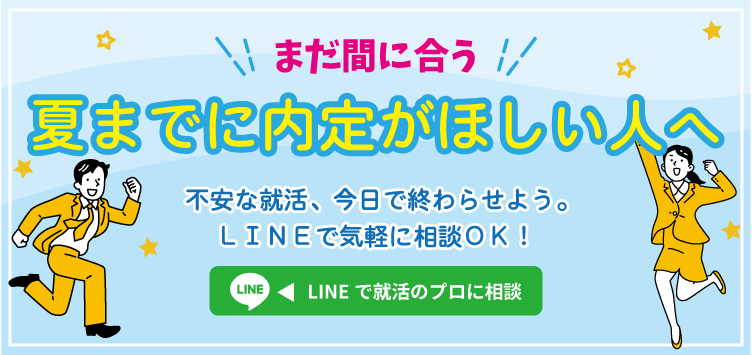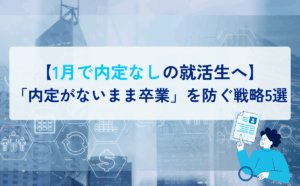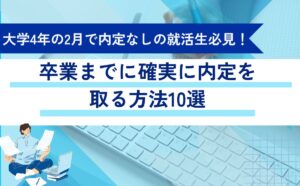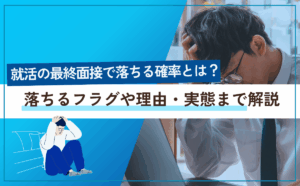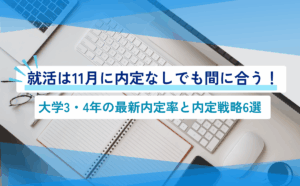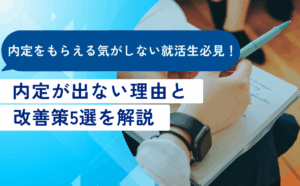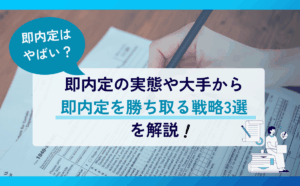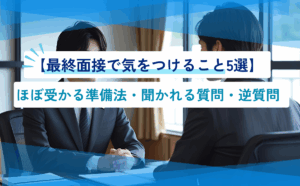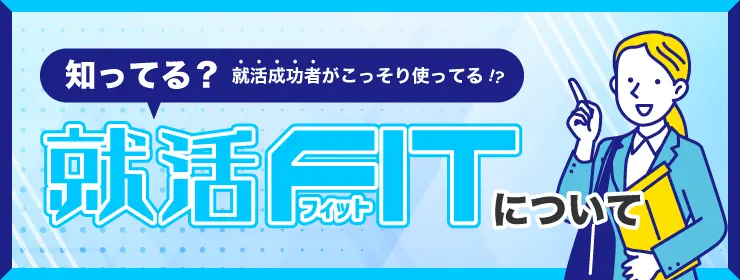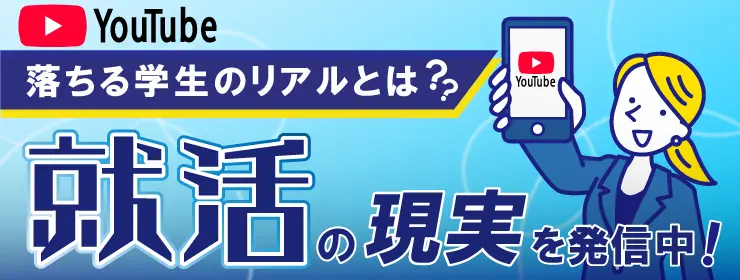今すぐ登録して
\勝つための就活を始めよう!/
【就活の悩み】行きたい業界がない時の対処法!興味のある業界の見つけ方
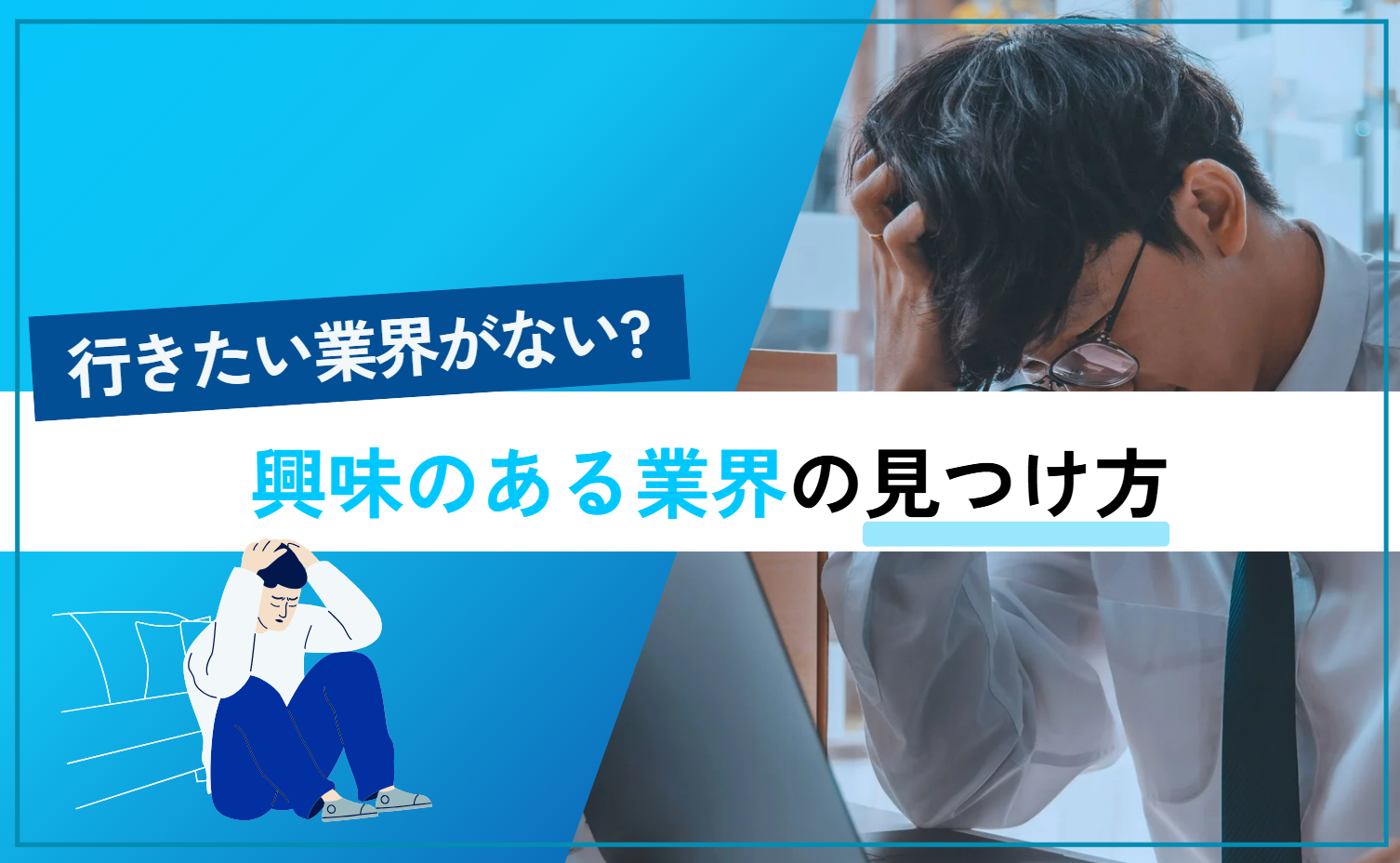
「就活を始めたけれど、行きたい業界がない……」と悩んでいませんか?
実は、同じ悩みを持つ就活生は意外と多いものです。
この記事では、業界選びに迷う理由や対処法、面接での答え方、興味のある業界の見つけ方を解説します。
- 就活で行きたい業界がなくて困っている就活生の方
- 行きたい業界を絞りたい就活生の方
「就活で行きたい業界がない」のは普通?
「就活で行きたい業界がない」のは普通なのでしょうか。
「行きたい業界がない」と悩む就活生は多い
特に、業界研究をする前の段階では、具体的なイメージが湧きにくいものです。
「とりあえず有名な企業を調べているけど、どれも自分に合っている気がしない」
「周りの友人は行きたい業界を決めているのに、自分だけ決まっていなくて焦る」
そんな不安を感じている人も多いのではないでしょうか?
しかし、行きたい業界が決まらないことは決して珍しいことではなく、むしろ多くの学生が経験することです。
まずは「業界が決まっていないのは自分だけじゃない」と安心してください。
就活で迷う理由
それでは、就活で迷う理由についてみていきましょう。
社会経験がないため、業界の違いが分からない
学生のうちは、アルバイトやインターンの経験があっても、実際の社会人としての業務経験はほとんどありません。そのため、
「○○業界と△△業界では何が違うのか?」
ということが、実感を持って理解しにくいのは当然です。
例えば、
IT業界とメーカー業界の違いは?
こういった業界ごとの特徴を知らないと、
「なんとなく聞いたことはあるけど、自分に合っているのか分からない」
と感じてしまうのです。
興味のある分野と仕事が結びつかない
「趣味や興味のあることはあるけれど、それを仕事にできるのか分からない」と悩む人も多いです。
例えば、アニメやゲームが好きな人が、
「エンタメ業界で働く」
といっても、具体的にどのような職種があるのか分からなければ、志望業界を決めるのは難しいでしょう。
また、
「好きなことを仕事にすべきかどうか?」
と悩むこともあります。
好きなことを仕事にすると楽しい反面、プレッシャーを感じたり、理想と現実のギャップに悩んだりすることもあるため、
「本当にこの業界でいいのか?」
と迷ってしまうのです。
「就活 行きたい業界 ない」人がやるべき3つの対処法
「行きたい業界がない」と感じる就活生がやるべき3つの対処法を紹介します。
自己分析や業界研究を進めることで、自然と興味のある分野が見えてくるはずです。
①自己分析で「向いている業界」を探る
行きたい業界がないと感じる場合は、まず自己分析を徹底しましょう。
自己分析をすることで、自分の得意なことや価値観を整理し、
「この業界なら自分に合いそう」
というヒントを見つけることができます。
自己分析のポイント
- どんな時にやりがいを感じるか?(例:「人の役に立つと嬉しい」「問題解決を考えるのが好き」など)
- どんな働き方をしたいか?(例:「安定した環境がいい」「挑戦できる環境がいい」など)
- どんなスキルを活かしたいか?(例:「文章を書くのが得意」「人と話すのが好き」など)
自己分析を深めることで、自分の適性に合った業界を見つけやすくなります。
②各業界の特徴を知る
まずは、各業界の特徴について知りましょう。
業界研究を進めることで、
「なんとなく知らなかったけど、興味を持てる業界」
が見つかることもあります。
例えば、「IT業界=エンジニアばかり」と思っていた人が、マーケティング職や人事職があることを知り、興味を持つこともあります。
③実際に企業を調べてみる
実際に企業を調べてみるのも一つの手です。
業界にピンとこなくても、企業単位で調べることで
「この会社の雰囲気が好き」
「この会社の理念に共感できる」
と感じることもあります。
面接で「志望業界が決まっていない」と答えるのはNG?
面接で「志望業界が決まっていない」と答えるのはNGなのでしょうか。
「志望業界が決まっていない」とそのまま伝えるのはNG
面接で
「まだ志望業界が決まっていません」
と正直に答えると、企業側に
「この人は就活の軸が定まっていないのでは?」
と不安を与えてしまいます。
企業は、入社後に活躍できる人材を求めています。
そのため、「業界が決まっていない=キャリアに対する意欲が低い」「他の企業とも適当に面接を受けているのでは?」とネガティブな印象を持たれる可能性があります。
では、どうすれば良いのでしょうか?
業界が決まっていなくても、「自分なりの就活の軸」 を持ち、それに沿って企業を選んでいることを伝えることが重要です。
面接官が見ているポイント
面接官は、以下の3つのポイントを確認しています。
就活の軸(企業選びの基準)があるか
業界が決まっていなくても、企業選びの基準を持っていれば問題ありません。
例えば、「人の生活を支える仕事がしたい」「成長環境がある会社で働きたい」など、自分なりの価値観や基準を伝えることで、納得感のある回答ができます。
どのように業界を選ぼうとしているか
面接官は、あなたがどのように志望業界を見つけようとしているのかをチェックしています。
たとえば、「自己分析をしながら、自分の強みを活かせる業界を探している」「実際に働く人の話を聞いて業界を絞っている」と伝えれば、前向きな姿勢をアピールできます。
企業に興味を持っているか
たとえ業界が決まっていなくても、「なぜこの企業の面接を受けたのか?」を明確に説明できればOKです。
企業の理念や事業内容に共感した点を伝えることで、「この人はしっかり企業研究をしているな」と好印象を持たれます。
逆転内定の最短ルートをご案内!
実際に登録から 17日で内定 をもらった先輩も!
興味のある業界の見つけ方
では、どのように興味のある業界を見つければ良いのでしょうか?
以下の5つのステップを参考にしてください。
1. 自己分析をする
まずは、自分がどんな仕事に向いているのかを知ることが大切です。
自己分析をすることで、「どのような業界・職種が自分に合いそうか」のヒントが見えてきます。
自己分析の方法
- 過去の経験を振り返る(アルバイト・サークル活動・学校の授業などで楽しかったことを思い出す)
- 適職診断を活用する(無料の適職診断ツールを使う)
- 家族や友人に「自分の強み」を聞いてみる
例えば、「人と話すのが好き」という人は、営業職や接客業が向いているかもしれませんし、「データを分析するのが得意」という人は、IT業界やコンサル業界が合うかもしれません。
2. 業界・職種の情報を集める
業界研究を進めると、知らなかった業界や職種に興味を持つこともあります。
業界研究のポイント
- 就活サイトの業界図鑑を読む
- 企業説明会や業界セミナーに参加する
- 経済ニュースをチェックして、成長している業界を知る
例えば、「IT業界=エンジニアばかり」と思っていた人が、実はマーケティング職や人事職もあることを知り、興味を持つこともあります。
3. 企業単位で興味を持てるか考える
業界にピンとこなくても、企業単位で調べると「この会社の雰囲気が好き」「この会社の理念に共感できる」と感じることもあります。
企業のHPや採用ページを見て、興味を持てる企業がないか探してみましょう。
4. 実際に働いている人の話を聞く
実際にその業界で働いている人の話を聞くと、より具体的にイメージできます。
情報収集の方法
- OB・OG訪問をする
- 就活イベントや座談会に参加する
- 企業説明会で社員に質問する
たとえば、「思っていたよりも社風が合いそう」「意外と楽しそうな仕事が多い」と感じることもあります。
5. 職種ベースで考えてみる
業界ではなく、職種ベースで考える という方法もあります。
職種の例
- 営業職(人と関わるのが好きな人向け)
- 企画職(アイデアを出したり、戦略を考えるのが好きな人向け)
- 技術職(ものづくりや研究が好きな人向け)
- マーケティング職(データ分析や市場調査が好きな人向け)
「この職種なら面白そう」と思えるものがあれば、その職種を募集している企業を探してみましょう。
まとめ
行きたい業界がないと感じるのは、決して珍しいことではありません。
しかし、自己分析や業界研究を進めることで、自分に合った業界を見つけることができます。
面接では「志望業界が決まっていない」とそのまま伝えるのではなく、「企業選びの基準」や「企業に興味を持った理由」を明確にすることが大切です。
焦らずに、自分に合った業界を見つけていきましょう!
「就活FIT(フィット)」なら、業界研究のポイントや企業選びのコツを徹底解説!
ES・面接対策からキャリアプラン設計まで徹底支援し、あなたにピッタリの業界・企業選びをサポートします。今すぐLINEで無料相談!